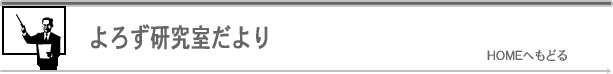
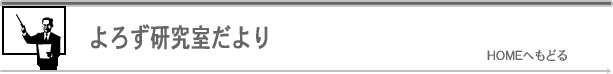
■冷凍すりみの製造方法
| ■原料処理 原料魚→原料処理と洗浄(洋上すり身生産では魚体処理にヘッドカッター、フィレマシーンを導入しているが、陸上すりみの原魚処理は人手でおこなわれている。)魚体処理に機械が使われない理由としては、魚卵の損傷率が高いことと、魚体のサイズが不揃いで人手にくらべて歩留まりが悪いためである。 魚体の洗浄は処理後ただちに一度洗浄したものを採肉前に更に洗浄する二度洗いが一般的である。   |
| ■採肉工程 採肉の方法は採肉効率のよい大型ロール式が主流になっている。  |
| ■水晒し工程、 水晒し用の水の水質は、製造中あるいは冷凍保管中に品質の劣化を招くカルシウムやマグネシウムを多く含んだ硬度の高いものや、銅、鉄などの重金属イオンの多い地下水は避けるべきで、pH値はたんぱく変性やかまぼこ形成能からみて中性附近が好ましい。  |
| ■夾雑物除去、脱水工程 当初、脱水後に裏ごしをかけていたが、裏ごし機は能率が悪く、発熱をともなうために肉質部のロスが多いといわれ、リファイナが開発された経緯がある。   |
| ■添加物の混合 脱水後は、ハイニーダー、サイレンとカッターなどを使用し、所定量の添加物を混合する。 無塩すりみであれば、糖類と燐酸塩、加塩すりみは食塩と糖類、ムリンすりみは糖類のみというような配合によって、すりみの種類が異なる。 これは、それぞれのできあがってきたすりみの経過による違いであり、基本的には練り製品の原料としての保管や劣化防止を目的としている。 (ただし、写真の舞鶴蒲鉾協同組合のすり身工場で製造している生すりみについては添加物は一切添加しておりません。冷凍しないので蛋白変性の心配がないからです。) |