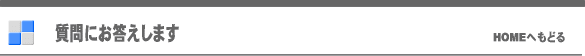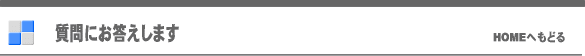|
1.ヒスタミン食中毒とは?
ヒスタミン食中毒とは、鮮度が低下したことによりヒスタミンが多く蓄積された魚介類やその加工品を喫食した直後に発生するアレルギー様食中毒で、その多くは集団給食施設や飲食店などで発生している。ヒスタミン食中毒は原因物質がヒスタミン(化学物質)であるため、わが国における食中毒統計では化学性食中毒に分類されている。しかし実際には、ヒスタミンは魚肉中に多く含まれているアミノ酸の一種である遊離ヒスチジンを原料としてヒスチジン脱炭酸酵素を有する微生物によって生成される。このような生成過程からみると、ヒスタミン食中毒は細菌性食中毒に分類されるべきものとも考えられる。
食中毒として大きなウエイトを占めるヒスタミン中毒は、口や食道、胃、腸の粘膜で抗体が結合して、主に消化器系のアレルギー疾患を起こすが、この症状は普通の人(アレルギー体質でない人)でも大量にとることによって発生する。 これはヒスタミンだけでなく、他の腐敗アミン類(アグマチン、フォスフォリルコリン、メチルグアニジンなど)の協労作用によって起こると言われているが、国立予防衛生研究所では、ヒスタミンの作用を起こすの相加するサウリンによってアレルギー様食中毒が起こることを明らかにしている。サウリンは自律神経毒で、酸や加熱に対して強く、水には溶けるが、無水アルコールには溶けにくい性質がある。
2.ヒスタミン産生に関与する微生物
ヒスチジン脱炭酸酵素を有する菌(ヒスタミン産生菌)には、 Morganella morganii
(モルガン菌)や Klebsiella oxytoca を代表とする腸内細菌、そして好塩性ヒスタミン産生菌である
Photobacterium phosphoreum や P. damselae
などが知られている。これらのヒスタミン産生菌が付着した魚介類やその加工品の保存温度が不適切な場合や長期保存した場合には食品中で菌が増殖し、その結果としてヒスタミンが魚肉中に蓄積するため、これらを喫食すると食中毒になる。
ヒスタミン産生菌のうちモルガン菌を代表とする腸内細菌は主に漁獲後に魚に付着する二次汚染菌と考えられている。一方、もともと海水中に生息している好塩性ヒスタミン産生菌は魚に付着する一次汚染菌として存在している。これらのヒスタミン産生菌には中温域で発育する菌のほかに、10℃以下でも発育する低温性菌が存在するため、低温で流通している魚介類・加工品においても食品衛生上重要視すべき菌である。
3.原因食品
ヒスタミンが生成される原料となる遊離ヒスチジンは、マグロ、イワシ、サンマなどの青魚(赤身の魚)に多く含まれていることから、本食中毒の原因食品のほとんどは魚介類である。まれに、鶏肉、ハム、チェダーチーズが原因となった例もある。
このように、調理したり、加工してあるから安全であるという、従来の食中毒に対する概念ではヒスタミン中毒は防止することはできないことに留意すべきである。
1960年から1978年までの19年間に全国で発生したヒスタミン食中毒事件は99件あり、そのすべては表層性の回遊魚によるものである。
4.症状
ヒスタミン食中毒の多くは、喫食直後から1時間程度という短時間で発症する。その症状は舌のしびれ、顔面の紅潮、発疹、吐き気、腹痛、下痢などであるが、症状自体は軽く、通常長くても一日で回復する。
5.予防法
日本では魚介類の消費量が多いため、諸外国に比べて、ヒスタミン食中毒を起こす機会は多い。ヒスタミンは熱で分解されにくいため、加熱処理により菌は死滅したとしても、一度産生、蓄積されたヒスタミンを取り除くことは困難である。また、ヒスタミンは腐敗により産生されるアンモニアなどと違い、外観の変化や悪臭を伴わないため、食品を喫食する前に汚染を感知し回避することは非常に困難である。 そのため、鮮度が悪くヒスタミンが形成されたものは、刺身や酢の物だけでなく、煮つけや焼き物に調理だれても、また、干物やみそ漬け、ぬか漬け、缶詰などに加工されても中毒事件が発生するので厄介である。喫食中に、唇や舌先にピリピリと刺激を感じた場合は速やかに食品を処分することが大切である。
ヒスタミン食中毒の予防には、食品の保全に注意を払うことが最も大切である。特に夏の時期、買った魚はその日のうちに食べ、仮に残った場合でも冷蔵庫内での長期保存を避け、速やかに冷凍するよう心がけたい。
|